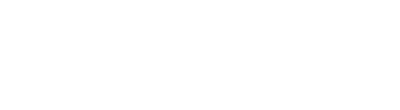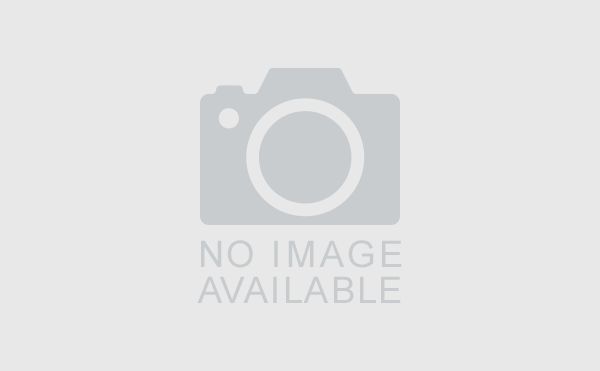2004年のHPC(その六)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、2004年の連載の終盤を迎えています。先週(j)と今週(k)は、PittsburghのSC2004の「その二」と「その三」です(3回に分けて連載)。
「地球シミュレータ」は、2004年の6月まで連続5回(2年半)に渡って35.86 TFlopsで首位を独占し続けてきましたが、今回遂に首位の座を明け渡し、3位に落ちてしまいました。LLNLのBlueGene/LとNASAのColumbiaは、抜きつ抜かれつ首位争いを繰り広げました。上位の入れ替わりは激しく、Top10の半分は新顔でした。日本としては、地球シミュレータを別にすれば、Top20内は理研のSuper Combined Clusterの14位だけという寂しい結果に。
招待講演の一つでは、国防省のHolland氏が、アプリケーションにおける実用性能の重要性を指摘しました。OSCのAhalt氏は、Blue Collar Computing(High endとlow endとの中間)を充実させよ、と述べました。
Seymour Cray賞では、3回目(最後)の選考委員を務めましたが、受賞者のBill Dally教授は、バンド幅の重要性を強調しました。
“Supercomputer architecture, it’s about bandwidth, not MFlops”
Gordon Bell賞では、地球シミュレータが2002年以来3年目の連続受賞となりました。陰山 et al.は、地球ダイナモのシミュレーションで15.2 TFlopsを達成し、坂上 et al.は、HPFで流体シミュレーションを行い14.9 TFlopsを出し、横川 et al.は一様等方乱流のDNSで16.4 TFlopsを出しました。HPFでTFlopsが出たことは驚きをもって迎えられました。
5年目となるバンド幅チャレンジでは、”Third Generation Data Reservoir”の名前でエントリした平木等のグループが” Single Stream, Longest Path, Standard MTU TCP Throughput”賞で連続3回目の受賞をしました。Honorable mentionでは、九州大学らのグループが”Showing Bandwidth of CJK (China, Japan, Korea)”のエントリで受賞し、JAXAのグループが” Effective Rapid Remote File System For Supercomputer Users Who Are Not Network Expert”のエントリで受賞しました。Honorable mentionまで含めれば、6件中3件が日本関係でした。
最終日、金曜日午前のパネルの一つで、松岡聡(東工大)が英語力を駆使して大活躍しました。
次回は、アメリカの企業の動きで、Hewlett-Packard社は64ビットサーバにOpteronを採用すると発表し、Itaniumの退潮を印象づけました。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫