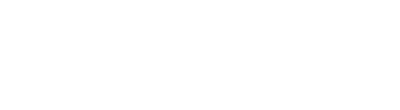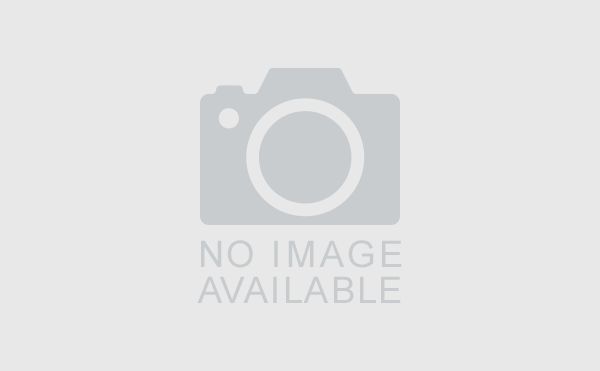2005年のHPC(その三)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、3月3日から2005年に入っています。12回連載の予定です。先週226回(d)と今週227回(e)の内容を紹介します。(d)は国内会議、(e)は日本の企業の動きと標準化です。
HPC関連の国内での会議はどんどん増えているので、私の把握した範囲で紹介しています。和光で行われた「理研シンポジウム」では、(最後の)RIKEN BMTコンテストが行われましたが、同時にベンチマークプログラムの公募も行いました。以前から性能評価の研究を主導している関口智嗣氏は、SPEC HPGでの議論を紹介して、ベンチマーク設定の困難さを指摘しました。
つくば国際会議場で開催されたSACSIS 2005では平木敬氏が「EFLOPS, 10Tbpsの世界を目指して」と題して基調講演を行いました。BlueGene/Lが100 TFlopsをやっと越した時点でExaとはさすが平木氏です。
SWoPP 2005は佐賀県武雄でした。長崎新幹線の高架橋ができていました。
第4回情報科学技術フォーラムFIT2005では、『スパコン日本の時代は取り戻せるか』というパネルが企画され、筆者が司会を仰せつかりました。
富士通研究所に「ペタスケールコンピューティング推進室」が設置され、2010年度末までにピーク3 PFlopsの次世代スーパーコンピュータを稼働させると発表しましたが、海外では、日本の次世代の目標が3 PFlopsだという誤解も生れました。
1月、中野守氏がHewlett-Packard社を辞めてクレイ・ジャパン・インクの社長に就任したことが大ニュースでした。独立後のCray Japanとしては初の専任社長でした。
IBMのBlueGene/Lが売れています。産総研の生命情報科学センターには2月に4ラック導入され、KEKには合計10ラック導入予定と発表されました。
CHOKKAで有名な平成電電が自転車操業で破綻し、傘下に入ったベストシステムズ社がどうなるか心配しました。西克也氏によると大けがはしなかったそうですが、いろいろ大変だったようです。
Grid標準化ではGGFがソウル、シカゴ、ボストンと3回開かれました。Globus Allianceに加えて、Globus Consortiumができたので、スワ分派活動かと一時緊張しました。
IECでは二進接頭語にZebiとYobiを追加しました。こんなの使うことがあるのでしょうか。
次回は、アメリカやヨーロッパの政府主導の動きです。アメリカはHPCの主導権を握れるのか?!
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫