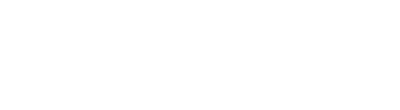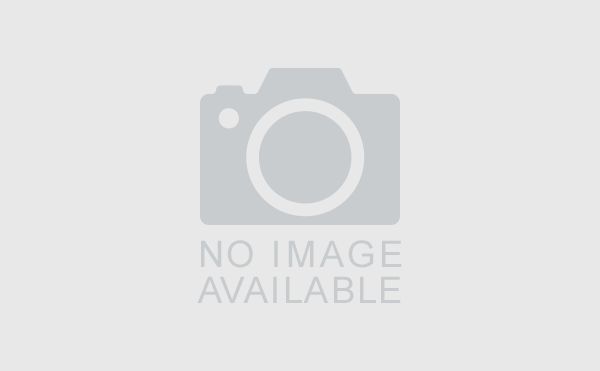2006年のHPC(その四)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、2006年の歩みを書いています。先週の新HPCの歩み(第240回)-2006年(f)-と、本日公開の新HPCの歩み(第241回)-2006年(g)-についてご紹介します。(f)は「日本の企業の動き」と「標準化」、(g)は「アメリカ政府の動き」です。
次世代スーパーコンピュータ開発プロジェクトでは、日本電気・日立チームと富士通が、それぞれ10 PFlopsを目指す概念設計を実施しました。
日本電気は、演算器を2倍に増やしたSX-8Rを発表しました。要素技術では2 5Gbpsの直接変調動作が可能な面発光レーザーの開発に成功しました。
富士通は、dual-core Itanium2 (1.6 GHz)を搭載したサーバPRIMEQUESTを岡崎共通研究施設 計算科学研究センターに設置しました。
日立は、SR11000/K1を、気象庁や高エネルギー加速器研究機構に設置しました。
日本IBMは、CellやBluegene/L関係のセミナーを盛んに開催しました。
標準化では、グリッド標準化を目指すGGFと、グリッドの企業利用を促進するEGAとが合併しOGF (Open Grid Forum)を設立しました。GGF会議も3回開かれています。
アメリカのブッシュ大統領は、競争力が強化されるようアメリカのイノベーションを奨励すると述べました。HPCにも多額の投資が行われています。
LANLは、PFlops級のスーパーコンピュータRoadrunnerの提案を公募し(名前が先についている)、16000個のCell B.E. (Broadband Engine)とAMD社のx86プロセッサOpteron 16000コアからなるIBMの提案を採択しました。2008年に、最初にLinpackでPFlopsを超えるマシンとなります。全予算は$110M。
ORNLではCray社のJaguarを導入すると発表しました。これもPFlops級を謳っていましたが、一番にはなれませんでした。
SNLでは、Red Stormの更新が進む一方、1996年12月に初めてTFlopsの壁を越え、1997年6月のTop500でCP-PACSに代わって1位を取ったASCIの最初のスーパーコンピュータASCI Redは2006年6月29日をもって、ついにシャットダウンとなりました。「アディオス、ASCI Red」のケーキが作られました。
NERSCではHorst Simonが所長辞任の意向を表明しました。2008年1月にKathy Yelickが所長に就任します。
NSFでは、TeraGridの資源提供機関が増えています。最初はItanium色が濃厚でしたが、しだいに多様性が増えています。
DARPAでは、HPCSのPhase IIIが発表され、Sun Microsystems社が撤退しました。
次回は、ヨーロッパの政府関係の動き、中国の動き、世界の学界、および国際会議(その一)です。中国製のCPUチップ「龍芯」や「申威」などが登場します。「漢芯」はfakeでしたが。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫