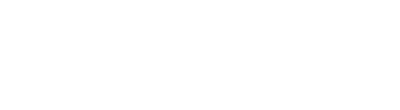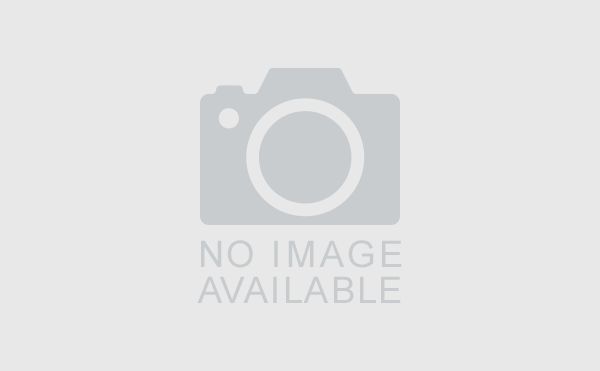2006年のHPC(その六)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、2006年の記事も終わりに近づきつつあります。先々週の新HPCの歩み(第244回)-2006年(j)-と、昨日公開の新HPCの歩み(第245回)-2006年(k)-についてご紹介します。先週は休みました。(j)はドレスデンで開催されたISC2006、(k)はタンパで開催されたSC06です。
これまで何回かハイデルベルクで開催されていたISC2006は、より会場の広いドレスデンに移りました。建都800年にあたり、また爆撃で破壊された聖母教会の再建も前年完了しました。私もドレスデンは初めてでした。折からドイツでワールドカップが開催中で、町中が浮かれていました。
Top500は、トップは相変わらずBlueGene/Lでしたが、東京工業大学のTSUBAMEが7位に登場し、地球シミュレータを超えたことが注目を浴びました。「しかもUS Technologyで作られている」とStrohmaierが強調しました。20位以内で日本国内設置は、他に産総研のBlue ProteinとKEKのMOMOとSakura(いずれもBlueGene/L)でした。
Horst Simonを座長に” the Asian Attack”というセッションが設けられ、私が日本の次世代計画について公開されている範囲で発表しました。Steve Chenは中国のHPCの最近の勢いについて講演しました。
なお、この年まではInternational Supercomputer Conferenceと名乗っているようです。
タンパのSC06は推薦入試と重なって出席できませんでしたが、渡辺貞氏(当時、理研次世代スーパーコンピュータ開発実施本部)がSeymour Cray賞を受賞しました。受賞記念講演の最後に、「私がこの賞をいただけたのは三好氏のおかげである。三好氏に感謝している」と述べました。
日本から採用された論文は1件でしたが、これは、産総研グリッド研究センター、名古屋工業大学、USCの共同研究によるもので、古典分子動力学、量子論的分子動力学の混成問題を、世界に広がったグリッド上で解く技術を開発しました。日本発のグリッド・ミドルウェアNinf-Gが活用されています。
Jack Dongarraが主導するTennessee大学のグループは、いくつかのプロセッサで単精度演算が倍精度演算より2倍から10倍も速いことから、混合精度演算で、倍精度演算と同等な結果をより高速に得られることを示しました。
Gordon Bell賞は、6件のfinalists中4件が日本のグループの成果でしたが、受賞は他の2件でした。MDGRAPE-3を使ったプリオンのシミュレーションはHonorable Mentionとして賞賛されました。筑波大・KEKのグループがStorage Challengeで受賞したことも大きな成果でした。
Top500では、20位以内は東工大のTSUBAMEと地球シミュレータだけになってしまいました。
次回は、アメリカの企業の動き(その一)です。IBM社はCell Broadband Engineを採用したブレードサーバーを開発したと発表しました。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫