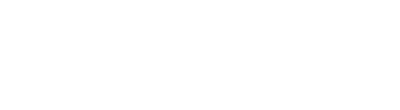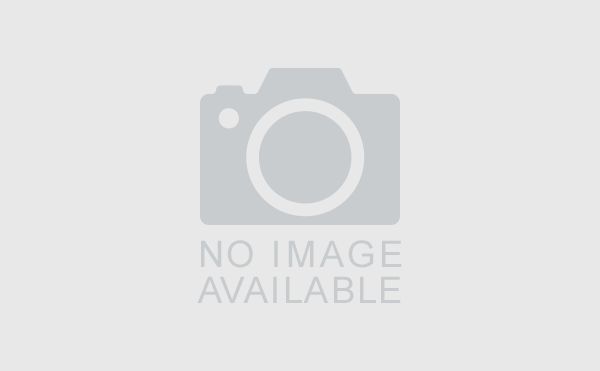2007年のHPC(その一)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、本日公開の「新HPCの歩み(第248回)-2007年(a)-」から2007年に入りました。今回は、「次世代コンピュータ開発」(後の「京」)の「その一」です。
3月28日、理研は次世代スーパーコンピュータ施設の立地地点として、神戸のポートアイランド第2期地区を選んだことを発表しました。仙台(東北大学サイバーサイエンスセンターの南側の空き地)も有力候補だったようです。報道によると、「神戸市は、約40億円の土地を無償貸与し、さらに拡張用地も用意するといった大盤振る舞いが功を奏した」とのことでした。
文部科学省に次世代スーパーコンピュータ概念設計評価作業部会が設置され、理研の概念設計の評価を行いました。理研は、10 PFlopsのユニットA(富士通製、超並列スカラ)と、3 PFlopsのユニットB(日本電気・日立製、超並列ベクトル)を共有ファイルで結合した複合システムを提案しました。これで「統合汎用スーパーコンピュータシステム」「科学技術・産業の競争力を発展させる将来型システム」と言えるのか?ここでの議論は荒れに荒れました。
多くの委員に不満が残りましたが、6月12日、評価報告書が公表され、GOが出ました。富士通および日本電気・日立は7月4日から詳細設計を開始しました。この議論は2年後の事業仕分けまで長引きます。
この計画は実現不可能だから、2008年ごろ売り出される市販品を安く買えばよい、という批判がありました。2008年にそんなものは買えたでしょうか?
ちなみに、記事では名前を伏せましたが、「ボク、罰金の方がいいです」とつぶやいて役人に一喝されたのは天野英晴委員、「もっと上手に騙されたい」と叫んだのは、故中島浩委員でした。
次回は、「次世代スーパーコンピュータ開発の続き」および「日本政府の動き」です。アプリケーション検討部会は21個のターゲットアプリケーションを決定しました。NAREGIシンポジウム2007「グリッドで切り開く次世代研究環境」が一橋記念講堂で開催されました。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫