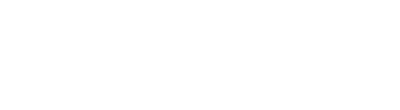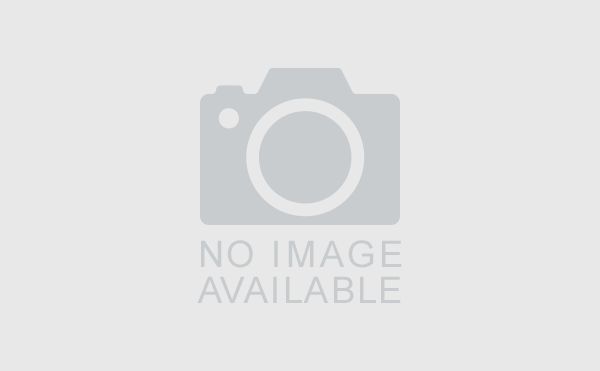2007年のHPC(その四)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、2007年の海外関係の動きを追っています。先週の「新HPCの歩み(第251回)-2007年(f)-」と「新HPCの歩み(第252回)-2007年(g)-」を紹介します。「アメリカ政府の動き」「ヨーロッパ政府関係の動き」「中国の動き(政府関係の企業関係の両方を含む)」「世界の学界の動き」です。
何でも「一番でなければならない」アメリカは、科学技術で世界の主導権を握るためにAmerica COMPETES Actを成立させます(何の省略かは本文参照)。エネルギー省科学局などの科学技術予算の大幅な増による研究開発の推進や理数教育の強化、ハイリスク研究の促進などを図る法律です。すぐ成果の出る研究ではなく、リスクを含む研究を謳っているところが、さすがアメリカです。
NSFでは、TeraGridの中核となる資源として、Track 1(第一階層)としてUIUCを選定し、Track 2(第二階層)にも複数の組織を選んでいます。アメリカの研究者に提供されます。UIUCは、日本の次世代スーパーコンピュータ計画とバッティングしそうです。
DOEも公募制の資源提供プログラムINCITEで、大学や国立研の研究者に大規模な資源を提供していますが、前年からは民間も対象としました。
DARPAのHPCSはPhase IIIとして、Sun社を落とし、IBM社とCray社を選定しました。IBM社はPERCSを、Cray社はCascadeを開発し2 PFlops以上を目指します。10 PFlopsに行くと、また日本と競合します。
ヨーロッパでは、15国がスーパーコンピュータ資源を共同利用するPACEイニシアティヴの合意書を結びました。イギリスでは、EdingburghにHeCTORを設置します。その他の国々も大規模な資源を用意しています。
中国でも、輸入したプロセッサを使ったHPCだけでなく、自前のプロセッサ「龍芯」を使ったHPCも開発しています。まだあまり性能が出ないようです。6回目のChina HPC Top100が発表されましたが、上位にゲーム会社が目立ちます。
アカデミアの動きとしては、超並列ではトランジスタ数より電力の方が問題だという認識が広まってきました。その後、演算よりデータ移動の方が電気を食うということが問題になります。
PFlopsが目前ということで、”Petascale Computing”という本が出ました。
Ken KennedyやJohn Backusが死去し、Jim Grayが行方不明になりました。
次回は、国際会議です。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫