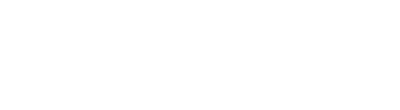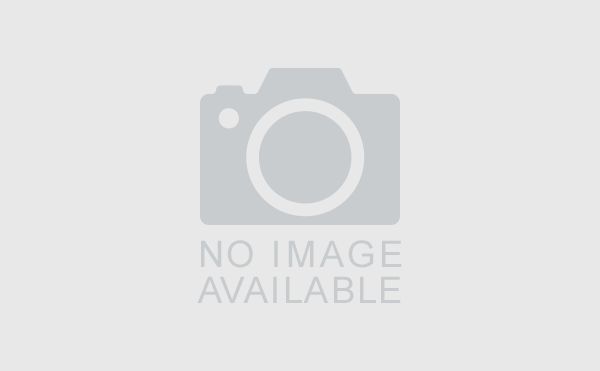2007年のHPC(その五)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、2007年の国際会議の動きを追っています。先週の「新HPCの歩み(第255回)-2007年(h)-」と「新HPCの歩み(第256回)-2007年(i)-」を紹介します。
2007年もHPC分野で多くの国際会議が開かれました。
(単体)トランジスタの時代から続く最古の会議ISSCCでは、半導体の新しい動向が発表されました。Intelは後で問題になるTeraFlops chipを発表しました。チップ上80コアですが、IA32(x86)でもIA64(Itanium)でもない命令セットでした。
同じく半導体の会議HOT CHIPSでは、CMOSの次は何かについてPanelで討論されました。30 qubitsの量子計算がイオントラップで近々実現できるとの発表がありましたが、ちょっと早計ではないでしょうか。
HPC Asia 2007はソウルで開催され、前日には情報処理学会のHPC研究会も同所で開催されました。
ICPP 2007は、初めて中国(西安)で開催されました。
第22回のISC2007は、旧東ドイツのDresdenで開催されました(昨年に続き二回目)。この年から論文の募集が行われ、審査の上講演が行われました。
企業展示では、IBM社がBlue Gene/Pを発表しました。また、Sun Microsystems社は、Magnumという巨大なInfinibandスイッチを展示しました。TACCの新システムで使われます。
私が印象に残っているのはNVIDIA社です。これまでグラフィック用のGPUを製造していましたが、汎用的なプログラミングを可能にするCUDAを発表し、64ビット演算も本格的にサポートするとのことでした。ついに、HPCに舵を切ったな、と実感しました。ただ、16ビットや8ビットも大活躍することは予見できませんでした。
Top500ではBlueGene/Lが相変わらずトップです。日本設置のマシンは20位までに、TSUBAMEと地球シミュレータだけになりました。寂しいが、この後、もっと寂しくなります。全体としては、Mooreの法則は続きそうでも、電力の壁が問題になり始めています。
Tom Sterlingは、過去一年を振り返って、「マルチコアが次のMooreの法則だ」と語りました。Manycoreの次はMyriadcoreか、というジョークを出しました。
次回は、ISC2007の続きとSC07の第一回です。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫