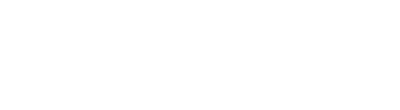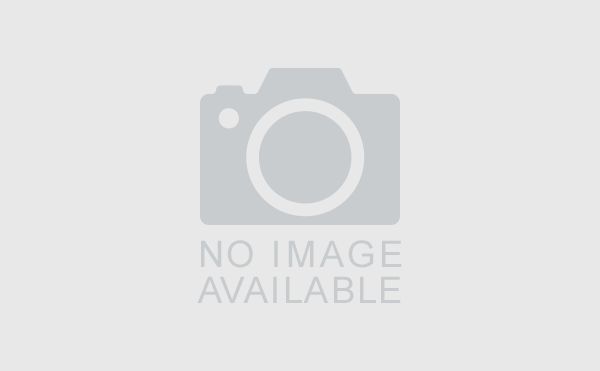2004年のHPC(その五)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、2004年の9回目となりました。先週の(h)では国際会議、今週の(i)ではHeiderbergのISC2004と、PittsburghのSC2004(3回に分けて連載)のその一です。
昨年、西安で開催予定のCCP2003はSARSの蔓延のため延期され、2004年に北京でICCP6との共同開催の形で開催されました。
私が組織委員長という形で、大宮において開催されたHPC Asia 2004は、40℃近い酷暑の中で開催されました。文中の開催報告のリンクは切れていますが、JSTAGEにあります。https://doi.org/10.11540/bjsiam.14.4_395
記念すべきことは、Los Angelesにおいて“Workshop on General Purpose Computing on Graphics Processors (GP2)”が開催されたことです。今でいうGPGPUですが、この時点でGPUを科学技術計算に使おうとい先見の明には敬服します。CUDAが出るのはこの3年後です。SC2004でも、GPUクラスタを使って科学計算(Lattice Boltzmann)を行ったという論文が発表されました。この論文は20年後去年のSC24において、Test-of-time Awardを受賞します。Test-of-time Awardはいくつかの学会にありますが、何年もの流れを経ても価値を失わない、あるいはますます価値の増す先駆的な論文を表彰するものです。
もう一つ画期的なことは、10月、Santa Feにおいて“The Path to Extreme Supercomputing”というワークショップが開催されたことです。数十年後にZettaflopsが必要になるので検討するという趣旨ですが、実質的にはExaflopsへのキックオフであったと考えられます。それでも、当時最高性能の地球シミュレータの5桁上の性能を考えていることに脱帽します。アメリカのチャレンジ精神でしょう。その後毎年開催されました。
ISC2004には参加しませんでしたが、地球シミュレータは5回目で最後のTopを飾りました。20位以内の国内マシンは、あと理研のSuper Combined Clusterと、AIST Super Clusterだけで、寂しくなりました。
再びPittsburghで開催されたSC2004の企業展示では、地球シミュレータからTopを奪還したIBMがBlueGene/Lで盛り上がっていました。CrayはRed Stormの商用版が売れています。SGIはMIPSからItanium2に移行しました。
直前にATIP主催のChina HPC Workshopが開かれ、中国の現状が報告されました。中国は急速にHPCに傾斜し、TFlops級のマシンなどそこら中にごろごろしている感じでした。うかうかしていると日本は後塵を拝することになりそうです。
会議前にはSun HPC Consortiumも開催され、2日目だけ参加しました。Gridとその応用で盛り上がっていました。
次回は、SC2004の「その二」で、基調講演、招待講演、Top500などについて書きます。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫