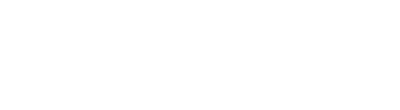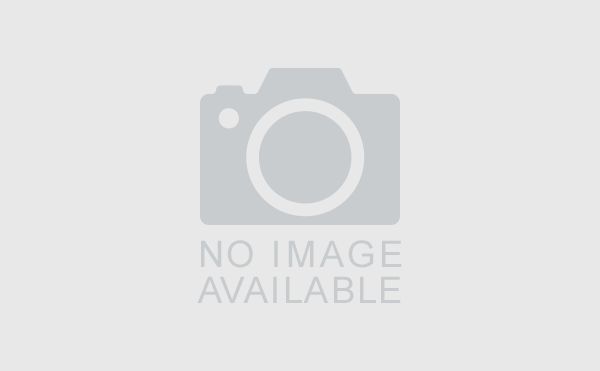xSIG 2025 CFP
HPC WORLD ML の皆様:
お世話になっております、xSIG 2025 プログラム委員長の大島です。
xSIG 2025 の論文募集をお知らせします。
Pre CFPでお知らせしましたとおり、xSIG 2025もSWoPP 2025内で開催します。
すでに論文投稿も可能となっております。
卒論・修論を元にした論文の投稿も大歓迎です。
幅広い分野からの投稿をお待ちしております。
https://xsig.ipsj.or.jp/2025/
https://easychair.org/my/conference?conf=xsig2025
xSIG 2025 CFP
(English follows Japanese)
———————————————————————
[Call for Papers]
xSIG 2025
The 9th Cross-disciplinary Workshop
on Computing Systems, Infrastructures, and Programming
(https://xsig.ipsj.or.jp/2025/)
【会期・会場】
会期 2025年8月6日 SWoPP2025内
会場 サンポートホール高松(香川県高松市)
【主催・協賛】
主催:
情報処理学会 システム・アーキテクチャ研究会 (ARC)
同 ハイパフォーマンスコンピューティング研究会 (HPC)
同 システムソフトウェアと
オペレーティング・システム研究会 (OS)
同 プログラミング研究会 (PRO)
共催: IEEE Computer Society Tokyo/Japan Joint Chapter
協賛:
情報処理学会 データベースシステム研究会 (DBS)
電子情報通信学会 コンピュータシステム研究専門委員会 (CPSY)
同 データ工学研究専門委員会 (DE)
同 リコンフィギャラブルシステム研究専門委員会 (RECONF)
【重要日程】
2025/3/11(火) 17:00 (JST): 論文登録〆切
2025/3/18(火) 17:00 (JST): 論文アップロード〆切
2025/4/29(火)頃: 採否通知
2025/7/ 8(火) 17:00 (JST): ポスター投稿〆切
2025/7/ 9(水)頃: ポスター採否通知
2025/8/4(月)-6(水): SWoPP 2025 開催 (xSIG2025は6日に開催)
xSIG (cross-disciplinary workshop on computing Systems, Infra-
structures, and programminG) は,JSPP,SACSIS,ACSI の伝統を受け継ぎ,
2017年より新たに始まった国内会議です.全主催・協賛研究会の分野にまたがる
(cross-SIG) 幅広い分野を対象とします.
xSIG は,これら分野にまたがる発表,議論の場を提供すること,および,
国際標準的なピアレビューを行って若い研究者を育成することを目指していま
す.特に,
・xSIGで得られたフィードバックを基に研究を進展させ,国際学会やジャーナ
ルへと歩を進めることを期待します.予稿集を発行しませんが,採択された
論文は,会議期間中,会議参加者のみに対して提供します.また,昨年までに
引き続き,情報処理学会ACS論文誌ではxSIG連携号を準備しています.xSIGの
次のステップの一つとして投稿をご検討ください.
・国際標準的な学会形式(査読を意識した投稿,査読を受ける・する,PC会議
での議論など)を通じて,実質的なフィードバック,および,若い研究者への
査読論文執筆の訓練・練習の場を提供します.学生を含む若手研究者が,
論文査読やプログラム委員を早期体験する機会としてヤング・プログラム委員
制度を設けます.
・学生を対象とする賞を多く設けます.
2020年より,xSIGは国内のコンピューティングシステム関連の研究会が一堂に
会する機会であるSWoPPの中で開催しています.
【xSIGの有料化について】
xSIG2024までは前身であるSACSISの剰余金を用いて運営してきましたが、
その剰余金もほぼ使い切ったため、スポンサー収入および採択者の皆様に
少しずつ賄っていただきたいと考えています。
1採択あたり10,000円を情報処理学会のマイページからお支払いいただく予定です。
xSIGの継続的な実施のためご協力をよろしくお願いいたします。
【組織】
プログラム委員長
大島 聡史(九州大学)
プログラム副委員長
田崎 創(IIJ)
川上 哲志(九州大学)
山田 浩之(Scalar)
ポスター委員長
横山 大作(明治大学)
プログラム幹事
三木 洋平(東京大学)
組織委員長
中田 秀基 (順天堂大学)
組織委員
井上 拓 (IBM)
岩下 武史 (京都大学)
遠藤 敏夫 (東京科学大学)
小口 正人 (お茶の水女子大学)
鯉渕 道紘 (国立情報学研究所)
合田 和生 (東京大学)
五島 正裕 (国立情報学研究所)
田浦 健次朗 (東京大学)
竹房 あつ子 (国立情報学研究所)
滝沢 寛之 (東北大学)
津邑 公暁 (名古屋工業大学)
———————————————————————
[Call for Papers]
xSIG 2025
The 9th Cross-disciplinary Workshop
on Computing Systems, Infrastructures, and Programming
(http://xsig.ipsj.or.jp/2025e/)
[Date and Venue]
Date: Aug. 6, 2025 in SWoPP
Venue: Sunport Hall Takamatsu (Takamatsu-shi, Kagawa)
[Technical Sponsors]
Sponsors:
– IPSJ SIG System Architecture (ARC)
– IPSJ SIG High Performance Computing (HPC)
– IPSJ SIG System Software and Operating Systems (OS)
– IPSJ SIG Programming (PRO)
Co-sponsors:
– IEEE Computer Society Tokyo/Japan Joint Chapter
Support:
– IPSJ SIG Database Management System (DBS)
– IEICE Technical Committee on Computer System (CPSY)
– IEICE Technical Committee on Data Engineering (DE)
– IEICE Technical Committee on Reconfigurable Systems (RECONF)
[Important Dates]
– Mar. 11, 2025, 17:00 JST: Paper registration due
– Mar. 18, 2025, 17:00 JST: Paper upload due
– Apr. 29, 2025: Author notification
– Jul. 8, 2025: Poster submission due
– Jul. 9, 2025: Author notification (poster)
– Aug. 4-6, 2025: SWoPP 2025 (xSIG is held on 6)
[Scope and Objectives]
xSIG (cross-disciplinary workshop on computing Systems, Infra-
structures, and programminG) is a workshop from 2017,
inheriting the tradition of JSPP,SACSIS,and ACSI. It solicits
contributions from a wide range of fields related to computing systems,
infrastructures, and programming, spanning all areas covered by the
sponsoring special interest groups (cross-SIG).
The main objectives of xSIG are to provide a forum to present and
discuss research ideas among researchers spanning many fields and to
raise young researchers through a globally standard peer review process.
In particular,
– We hope authors of xSIG workshop to advance their research based on
feedback received and step up to submitting their work to
international conferences and journals. We do not publish
workshop proceedings. The papers presented in xSIG will be available
only to the audience during the workshop. For those who want to
publish their work, we collaborate with IPSJ Transactions on ACS for
Special Issue on xSIG.
– We hope to give authors substantial feedback as well as a place for
young researchers to practice/improve writing papers for review,
through the globally standard conference format of submitting papers
for review, receiving/writing reviews, discussing papers in the
program committee meeting, etc. For this, we establish
Young Program Committee alongside the regular Program
Committee and welcome the participation of young researchers
including students to it, for “an early exposure” of motivated
students to peer review work normally done by senior researchers.
– We award many students.
From 2020, xSIG is co-located with SWoPP event (Summer United Workshops
on Parallel, Distributed and Cooperative Processing), in which many SIGs
on computing systems held workshops.
[About the fees of xSIG]
Until xSIG 2024, we have operated the xSIG using the surplus funds of its
predecessor, SACSIS. However, since the surplus has been almost completely
used up, we would like to ask sponsors and accepted authors to gradually cover
the costs of the xSIG. We plan to require payment of 10,000 yen per acceptance
via IPSJ My Page. We would appreciate your cooperation in ensuring the continued implementation of the xSIG.
[Organization]
Program Chair
OHSHIMA, Satoshi (Kyushu University)
Program Vice-Chairs
TAZAKI, Hajime (IIJ)
KAWAKAMI, Satoshi (Kyushu University)
YAMADA, Hiroyuki (Scalar)
Poster Chair
YOKOYAMA, Daisaku (Meiji University)
Program Secretary
MIKI, Yohei (The University of Tokyo)
Organizing Chair
NAKADA, Hidemoto (Juntendo University)
Organizing Committee
INOUE, Hiroshi (IBM)
IWASHITA, Takeshi (Kyoto University)
ENDO, Toshio (Institute of Science Tokyo)
OGUCHI, Masato (Ochanomizu University)
KOIBUCHI, Michihiro (National Institute of Informatics)
GODA, Kazuo (The University of Tokyo)
GOSHIMA, Masahiro (National Institute of Informatics)
TAURA, Kenjiro (The University of Tokyo)
TAKEFUSA, Atsuko (National Institute of Informatics)
TAKIZAWA, Hiroyuki (Tohoku University)
TSUMURA, Tomoaki (Nagoya Institute of Technology)