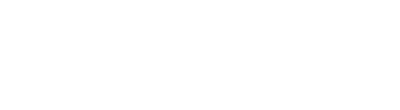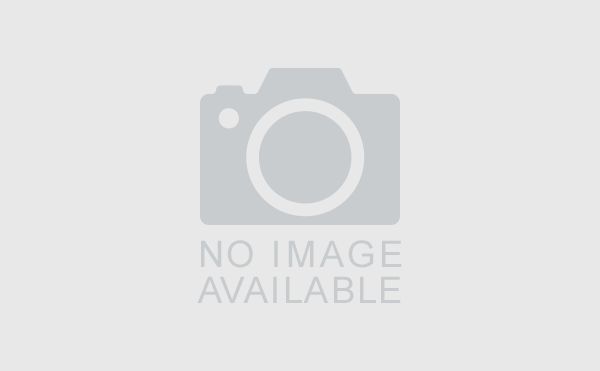2005年のHPC(その四)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、2005年の中盤に差し掛かりました。先週228回(f)と今週229回(g)の内容を紹介します。(f)はアメリカ政府の動きとヨーロッパの政府関係の動き、(g)は世界の学界の動きと国際会議です。
アメリカは、地球シミュレータショックを抜け出して、やっとHPCの主導権を握り、計算科学が花開こうとしいているのに、ブッシュ大統領はPITAC(大統領情報技術諮問委員会)を終了させました。各界からは非難の声が上がっています。
(アメリカ)競争力協議会は、HPCは産業にとって不可欠なのに、投資によって得られる利益を正確に定量化できないために、産業界のHPC利用の推進が妨げられていると分析しました。
2004年には、DOE先進計算再活性化法が成立しましたが、2005年もHPC再活性化法が提出されました。下院は通過しましたが、どうも上院は通っていないようです。でも一定の政治的効果はあったと思われます。
DOEの比較的大型の資源提供プログラムINCITEの採択結果が公表されました。次回の公募からは、産業界からも申請を受け付けると発表しました。
ASCI(ASCと改名)の当初計画最後のマシンPurpleがLLNLで完成しましたが、Top500ではRmax=63.39 TFlopsに留まりました。ASCのもう一本の柱である同じLLNLのBlueGene/Lは、フル構成でRmax=280.6 TFlopsの性能を出しました。
ヨーロッパでは、Barcelona Supercomputer Centerが開所されました。初代マシンのMare Nostrumは前年から動いています。アイルランドでもセンターが開設されました。
BNLでは、QCD専用の超並列機QCDOC(10 TFlops)が2台設置されました。1台はDOEが、もう1台は理研が出資したものです。
GPUを一般科学技術計算に利用できるのではないかという関心が高まっています。CUDAができるのは2007年です。
LANLのWu-chun FengらがSC05においてGreen500を提唱しました。その論文はSC22においてTest of Time Awardを授与されました。最初のGreen500のリストが発表されたのは2007年です。
2005年も、世界中で多くのHPC関連の国際会議がありました。目についたものだけ紹介しました。
次回は、Heidelbergでは最終回となったISC2005について詳しく。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫