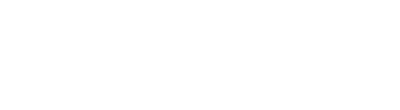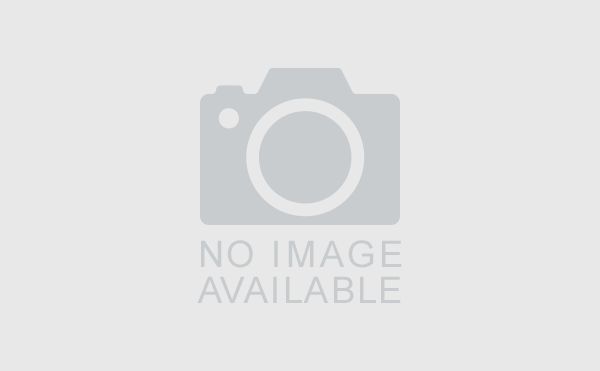2005年のHPC(その五)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、2005年の後半に入っています。先週230回(h)と今週231回(i)の内容を紹介します。(h)はHeidelbergで開催されたISC2005、(i)はSeattleで開催されたSC|05の「その一」です。
20回目のISCは最後のHeidelbergでの開催となりました。私も家内同伴で参加しました。次回はLeipzigです。
Sun Microsystems社がHPCに進出してきて、ISC2005に先立ちHPC Consortium Europe 2005が2日間にわたって市内のホテルで開催され、私も参加しました。同社はDARPAのHPCSのPhase IIを受注した3社の一つであり、盛り上がっていました。残念ながらPhase IIIでは脱落します。
ISC2005では25回目となるTop500が発表され、地球シミュレータは4位にまで落ちました。それだけではなく、1993年には110台あった日本設置のマシンが、今回は20台強に減っています。由々しき事態です。反面、中国の進出が著しい。Top10の半分はBlue Geneでした。
Tom Sterlingは、一年間を振り返って、この一年は「高密度実装計算」の年と総括しました。超並列でノード数が増えると、高密度実装が不可欠になり、当然熱の問題も出てきます。今に続く問題です。
第18回目のSC|05は、初めてシアトルで開催されました。この時も、先立ってSun HPC Consortium USA 2005が開催され、参加しました。最大のニュースは東京工業大学のTSUBAMEでした。
富士通のUser’s Meetingでは、Tony Heyの招待講演があり、Microsoft社がいかにHPCに積極的に取り組んでいるかを力説しました。
SCの基調講演の一つは、地元Microsoft社の会長兼Chief Software ArchitectであるBill Gatesでした。会場は超満員でした。とくに新しい話はありませんでしたが、Bill Gatesが講演すると様になるから不思議です。
Technical papersは全62件で、3件は日本からの論文でした。産総研からの“Full Electron Calculation Beyond 20,000 Atoms: Ground Electronic State of Photosynthetic Proteins”はBest Technical Paper Awardを受賞しました。日本からは初めてだと思います。原研からの“16.447 TFlops and 159-Billion-dimensional Exact-diagonalization for Trapped Fermion-Hubbard Model on the Earth Simulator”はGordon Bell賞のfinalistでしたが、惜しくも受賞を逃しました。JST CRESTの中島浩(豊橋技科大)のチームの1U当たり16基を高密度実装したMegaProtoクラスタの発表は、中島氏が熱弁をふるいました。
Exhibitor Forumも各社花盛りでした。本文をご覧ください。
次回は、SC|05の「その二」です。Top500や学術講演、各種Awardsなど。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫