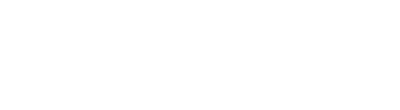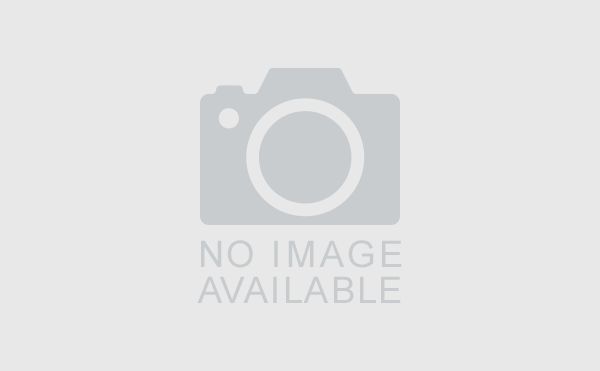2006年のHPC(その三)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、すでに2006年に入っています。先週の新HPCの歩み(第238回)-2006年(d)-と、本日公開の新HPCの歩み(第239回)-2006年(e)-についてご紹介します。(d)は「日本の大学センター等」「日本の学界の動き」、(e)は「国内会議」です。
大学センター関係では、センターの基本構想を転換させる2つの大事件がありました。それはTSUBAMEの稼働とT2K構想の発足です。ある意味で、その後の「京」や「富岳」にも連なる大変革、「(vender) catalog-drivenからtechnology-driven」への大転換でした。その萌芽は、NWTやCP-PACSにあったとも言えます。
東京工業大学(現、東京科学大学)では、前年のISC2005やSC|05で発表したように、AMD OpteronとCSX600を搭載したTSUBAMEを稼働させました。6月にはOpteronだけで36.36 TFlops(ピークの72.91%)を達成し、地球シミュレータを抜いて日本トップとなりました(地球シミュレータが日本トップだったのは、連続8回でした)。その後CSX600も稼働させてRmax=47.38 TFlopsを実現しました。
この成功を受けて、筑波大学、東京大学、京都大学のセンター関係者の間で、次期スパコンの基本設計を3大学共同で行うという構想(コード名Rhodes)が始まりました。9月6日に共同記者発表を行いました。いつの頃からかT2K (Tsukuba-Tokyo-Kyoto)と呼ばれるようになりました。詳細や経緯は本文をお読みください。ちなみに、ノーベル賞を受賞した加速器による長距離ニュートリノ実験T2K (Tsukuba to Kamiokande, Tokai to Kamiokande) とは関係ありません。
マイクロプロセッサによる超並列の時代を迎えてPCクラスタコンソーシアムが活発に活動しています。なおリンクしたプログラムなどが文字化けしていることがありますが、拡張機能のCharsetをインストールして、EUC-JPかISO2022-JPと設定すると読めます。
今年は日本初の真空管式電子計算機FUJICの完成(1956年3月)50周年、かつ情報処理学会創立45周年ということで、3月には盛大な全国大会を新宿の工学院大学で開催しました。工学院大学としては、4月の「情報学部」設立記念でもありました。私も初代学部長として走り回っていたはずですが、特別企画の記憶は飛んでいます。圧巻は、FUJICの実物大の写真でした。これだけは覚えています。
この年も多くのHPC関係の国内会議が開かれました。私は行きませんでしたが、2月のIPABシンポジウムではバイオナノやDNAコンピューティングが議論されています。12月のシンポジウムでは、引っ張り出されてHPCの歴史の話をしましたが、もう聞き飽きたのでは。
次回は日本の企業の動きと標準化です。次世代スーパーコンピュータ開発プロジェクトで、富士通と日本電気・日立製作所の2チームは概念設計を実施しました。グリッドではOGFが発足します。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫