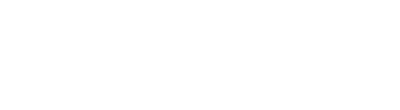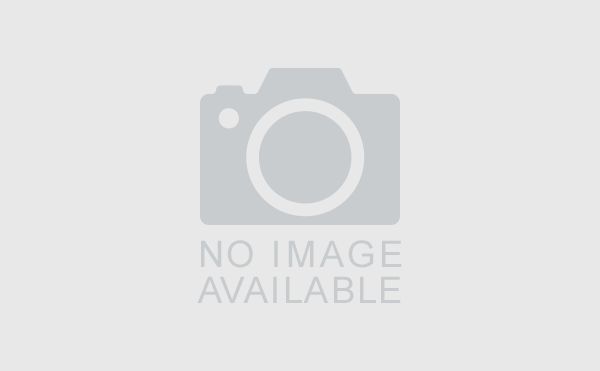2006年のHPC(その五)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、2006年の世界の動きに入っています。先週の新HPCの歩み(第242回)-2006年(h)-と、昨日公開の新HPCの歩み(第243回)-2006年(i)-についてご紹介します。(h)は「ヨーロッパの政府関係の動き」、「中国の動き」「世界の学界の動き」、「国際会議(その一)」、(i)は「国際会議(その二)」です。
ヨーロッパでは、政府の方針によりスーパーコンピュータが続々増強されています。中国政府は第11次五ヵ年計画の中で、電子情報通信分野では、情報産業の重要技術を掌握し、技術水準を世界のトップレベルに引き上げることを目標としています。
Texas大学Austin校の後藤和茂氏は、それぞれのプロセッサにチューニングしたGotoBLAS開発し、TACCはそれを公開しました。HPCwire紙は、後藤氏はどんなコンパイラもなしえない最適化を編み出し、「人間は機械に勝った」と書いていますが、20年後の今日、AIが発展しつつある現在、コーディングにおいて「人間はLLMに勝てる」でしょうか?
Toronto大学のGeoffrey Hinton博士らは、Auto-encoderの深層化に成功し、DL (Deep Learning)への道を切り開きました。Geoffrey Hintonは、John Hopfieldとともに、2024年のノーベル物理学賞を受賞しました。
第7回目となるVECPAR 2006は、初めてPortoを離れ、2006年6月10日~13日にブラジルのRio de JaneiroのIMPA(純粋応用数学研究所)で開催されました。
HPC関係では最古の国際会議ICPPは、記念すべき第35回がオハイオ州Columbusで開催されました。ICPPは1999年に会津若松で開催されて以来、「アジア」「北米」「ヨーロッパ」「北米」の順に4年周期で循環することとなりました。「北米」といってもカナダでの開催が3回続き、1998年のMinneapolisでの開催以来、久しぶりのアメリカ国内の開催となりました。
第4回となるGlobus World 2006は、GGF18およびGridWorldと合同で、2006年9月11日~14日にWashington DC Convention Centerで開催されました。2006年はGlobusプロジェクトの10周年です。
次回は、Dresdenで開催されたISC2006の詳報です。わたしも参加しました。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫