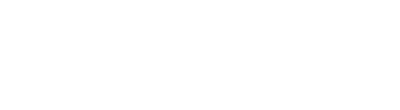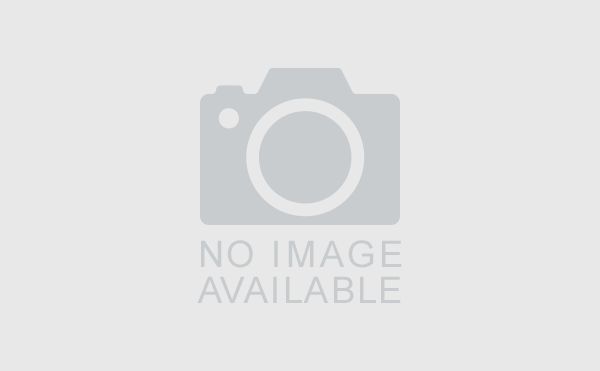2006年のHPC(その七)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、本日公開の「新HPCの歩み(第247回)-2006年(m)-」で2006年を終了しました。先週の「新HPCの歩み(第246回)-2006年(l)-」と合わせてご紹介します。「アメリカ企業の動き」「その他の企業」「企業の創業」「企業の終焉」です。
IBM社は、Cell B.E.を2基搭載したブレードサーバQS20を発売しました。2008年にLANLのRoadrunnerに搭載されるのはFP64の機能を増強したQS22です。
同じくIBM社は、Blue Geneのロードマップを更新し、Blue Gene/Qの目標ピーク性能を10 PFlopsと発表しました。2010年~2012年に実現するとのことで、日本の次世代スーパーコンピュータ計画とガチンコでぶつかります。
SGI社は、5月にChapter 11(連邦破産法第11章(よく11条と言いますが、Chapterは章です)、日本の民事再生法に相当)の保護を申請しましたが、なんと10月には脱しました。Bishop CEOは取締役に退き、Dennis McKennnaが会長兼CEOに着任しました。
Cray社は複数の製品ラインをXTシリーズにまとめるRainerプログラムを推進しています。これにより、FPGAも、ベクトル(X2)も、MTA (Eldorado)も統合されます。ORNLのJaguar (Cray XT4/XT3)はRmax=101 TFlopsで、6月のTop500で2位にランクしています。
Sun Microsystems社は、SPARCとともにAMD Opteronを搭載したサーバにも力をいれます。前述の東工大(現東京科学大学)のTSUBAMEもOpteron搭載のSun Fireから構成されています。Sun社はHPC業界に再挑戦しています。
Itaniumに足を取られていたIntel社は、Coreマイクロアーキテクチャのx86-64で、AMDを振り切ろうとしています。と同時に、1チップでTera Flopsを実現するCPU/アクセラレータを研究しているとの発表がありました。Larabeeという名前も聞こえてきました。しかし、これもこのあと迷走します。同社は10%(約1万人)の人員削減を余儀なくされます。
AMD社はIntel社に挑戦していますが、まるで「ダビデとゴリアテの戦い」(サムエル記上17章)と評されました。身長2.9mの巨人Goliath(Intel社)を、羊飼いの少年David(AMD社)が小石(CPU)で倒したからです。でも状況は急速に変わりつつあります。
AMD社は、なんと$5.4BでカナダのGPU会社ATI Technologies社を買収すると発表しました。CPU-GPUの統合を意図しているとの噂も。
他方、NVIDIA社はGPU向けの統合環境CUDAの構想を発表しました。実際に公開されるのは2007年です。
Steve Wallachら元Convex Computer Corporation関係者によりConvey Computer Corporationが設立されました。「x」を「y」に進めたようです。FPGAに基づくハイブリッドシステムを開発しています。SC06で、堂々デモを行っていました。
3月Amazon.comの子会社であるAmazon Web Service社(AWS社)は、Amazon S3 Cloud Storageを開始し、8月にはAmazon Elastic Compute Cloud (EC2)を開始しました。
次は2007年。次世代スーパーコンピュータは、神戸設置がきまります。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫