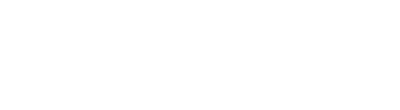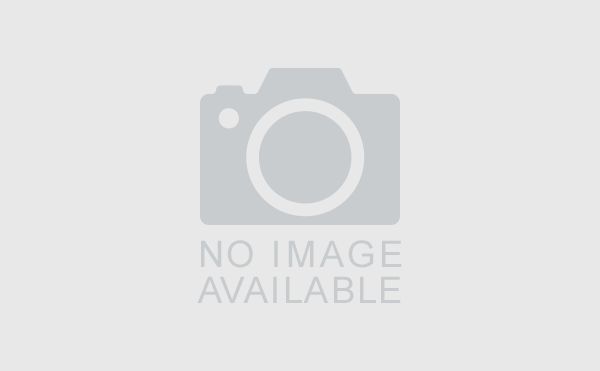2007年のHPC(その二)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、2週間前から2007年に入っています。先週の「新HPCの歩み(第249回)-2007年(b)-」と「新HPCの歩み(第250回)-2007年(c)-」を紹介します。先週の(b)は「次世代コンピュータ開発」(後の「京」)の「その二」と、「日本政府の動き」の「その一」、本日公開の(c)は「日本政府の動き」(その二)、「日本の大学センター等」、「日本の学界の動き」です。
理化学研究所のアプリケーション検討部会は、1年余りの議論を経て、次世代コンピュータのターゲットとするアプリケーション21個を決定しました。今後は、これを参照目標としてシステム開発を進めます。
また、理化学研究所は、10月、「次世代スーパーコンピュータシンポジウム2007 -ペタスケール・システムの利用に向けて」を丸の内明治安田生命ビル内MY PLAZAホール及びMY PLAZA会議室で開催しました。若手研究者のポスターが展示され、その中から最優秀賞、優秀賞を選考し、受賞者をSC07のレポータとして派遣しました。
2つのグランドチャレンジアプリケーション研究(ナノとバイオ)はそれぞれシンポジウムを開催しました。
総合科学技術会議の評価専門調査会では、国家的に重要な研究開発の評価「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用」についての原案が示され、了承されました。
地球シミュレータセンターでは、次世代スーパーコンピュータ計画が進む中での生き残り策として、「部品交換で能力を2倍にする」計画を概算要求しました。実質は更新なのですが、事情によりこういう言い方になりました。
JAXAでは、各事業所に設置されていた3つのコンピュータを1つに統合したJAXA Supercomputer System (JSS)を調布事業所に設置し、運用を開始しました。
JSTは、理事長を元科学技術庁次官の沖村憲樹氏から、高温超伝導で有名な元東大教授の北澤宏一氏に代えました。アカデミア出身の理事長は初めてです。
東北大学金属材料研究所は、BlueGene/Lの1/8 rackに相当する、「NIWS Gene/S Turbo」を導入しました。
次世代スーパーコンピュータの立地が神戸に決まり、神戸大学は他の3大学と共同して、大学院GP (Good Practice) 「大学連合による計算科学の最先端人材育成」を始めました。3年間のプロジェクトです。併せて、神戸大学では「計算科学」を軸にした新研究科を作る構想を始めます。
大阪大学は総合博物館を発足させ、1階の「コンピュータの黎明期」のコーナーには、さまざまな機械式計算機とともに、1950年に城憲三教授(1904-1982)が試作したENIAC型10進演算装置(真空管)を展示しました。
次回は、国内の会議です。PCクラスタコンソーシアムでは、3回のセミナーを開催し、PCクラスタの普及に努めます。SACSISではこれまでGrid Challengeに代えて、話題のCell B.E.を用いたマルチコアプログラミングコンテスト 「Cellスピードチャレンジ2007」を開催します。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫