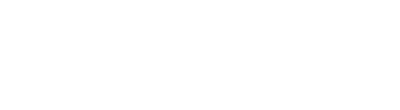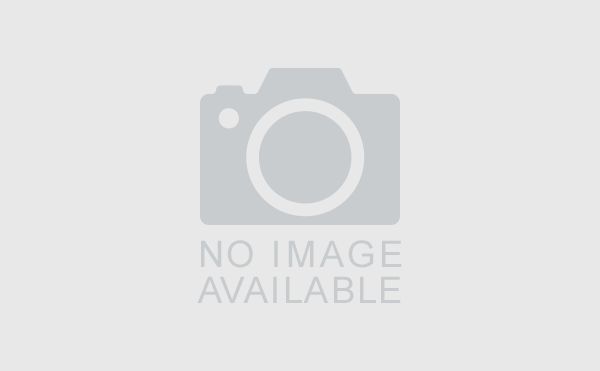2007年のHPC(その三)
「平成の語り部」小柳義夫です。電子ジャーナルHPCwire Japan https://www.hpcwire.jp/
に連載中の『新HPCの歩み』は、本日、2007年の国内関係の記事が終了しました。先週の「新HPCの歩み(第251回)-2007年(d)-」と「新HPCの歩み(第252回)-2007年(e)-」を紹介します。「国内会議」「日本の企業の動き」「標準化」です。
HPC関係の国内での会議は多く開催されています。前年廣安知之氏(同志社大学)を中心に発足した「Windows HPCコンソーシアム」は、Windows Compute Cluster Server 2003について幅広く活動しています。
PCクラスタコンソーシアムも、大阪と福岡でワークショップを開催しました。
NEC・HPC研究会、HAS研、SS研も、会員向けや一般向けの会合を盛んに開いています。
理研では、情報基盤センターと次世代スーパーコンピュータ開発実施本部の合同で、理研シンポジウムを和光で開催しました。
SACSISでは、J. Dongarra教授の基調講演と、横川三津夫氏の招待講演がありました。また、「Cellスピードチャレンジ2007」も開催されました。
新製品としては、日本電気がCPU当たり初めて100 GFlopsを超えるSX-9を発表しました。最大構成で800 TFlopsという発表でしたが、社員が言ったのか、記者が早とちりしたのか、BlueGene/Lに勝ったなどという記事が複数見られました。カタログ性能と実機の実測データを比較しても意味ありません。この次は、次世代スーパーコンピュータ計画のベクトル部分のSX-10か、と多くの人が考えました。
富士通は90 nmテクノロジによるSPARC64 VIプロセッサを発表しました。
グリッド関連では。初めてOGFを名乗ったOGF19を始めOGF21まで年内に3回開催されました。
Linux関係では、Open Source Development Labs(2000年創立) と Free Standards Group(2000年設立) が合併し、The Linux Foundationが発足しました。
次回は、アメリカ政府の動き、ヨーロッパの政府関係の動きです。連邦議会は、米国の競争力優位を確実なものとするためAmerica COMPETES Actを成立させました。アメリカは「二番」ではいけないのです。ヨーロッパも、CrayやIBMやNECなどのスーパーコンピュータを続々導入しています。
既発表記事の総目次はhttps://www.hpcwire.jp/new50history
にあります。ご愛読を感謝します。
小柳義夫